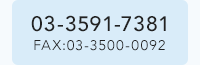セミナータイトル
「株式会社企業再生支援機構法の使い方と
他の企業再生手法との比較」
この間、我が国は、経済的に若干回復基調になったかと思えば、
信じがたいほどの急激な売り上げ減少に始まりまたしても、
大不況におそわれております。
当研究会は、経営困難に陥った意義ある企業の再生立ち上がりに
少しでも役に立ちたいと思い、
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などが集まり、
足掛け8年ほど企業再生の研究活動を続けて参りました。
企業再生の研究活動の一環として、
本年6月に成立した「株式会社企業再生支援機構法」についての
セミナーを開催いたします。
日時 平成21年8月7日(金)午後15時~18時
場所 東京
講師 内閣府政策統括官(経済財政運営担当)付
企業再生支援機構準備室
参事官 片桐一幸 氏
弁護士法人虎ノ門国際法律事務所所長
弁護士 後藤孝典
内容 1)株式会社企業再生支援機構法について解説
2)Q&A
3)休憩
4)民事再生、事業再生ADR、会社分割その他の再生手法との
比較検討
定員 80名
主催 一般社団法人日本企業再建研究会
株式会社企業再生支援機構法
2009.07.17 Friday 19:32 | 過去の研究テーマ | - | -
株式会社企業再生支援機構法
過剰債務と売上高の急激な減少を主因とする経営困難に直面して、今、さまざまな事業会社が苦境に喘いでいます。
この状況を克服するための方策の一つは、6月に成立した「株式会社企業再生支援機構法」による支援機構を活用する方法でしょう。
中小企業、中堅企業、その他の企業に対して同機構が提供する方法は、 政府出資の支援機構が、過剰債務を抱える企業に対する不良債権を銀行から買取り、その債権を「処分」するというものです。この「処分」の内容として、債権の転売やDES、またDES後の株式売却、債務免除など財務的な再生手法と、経営建て直しの事業手法とが用意されるだろうと考えらます。
産業活力再生特別措置法による事業再生ADRや第二会社方式、それに会社法上の会社分割とは違い、銀行保有債権の全面的買取りを骨子とする抜本的な方法が特徴であるといえるでしょう。
なお、本法は、平成20年通常国会に「株式会社地域力再生機構法案」という名称で提出されていたものが、参議院に提出された民主党法案「中小企業再生支援機構法案」が三セクを明示的に除外していたことをうけ修正され、さらに名称を「企業再生支援機構法」に改め、去る6月19日に成立したものです。
法律は本年の9月末までに施行される予定とされています。
以上 7月第93回目研究会テーマでした。